今回の記事では、無機化学で頻出の「気体の製法」の反応式を一挙公開します。頻出の気体の製法の反応式を書くことができれば、無機化学の得点が安定します。ここでマスターしましょう!
この記事を読んで以下のことを理解できればOKです↓↓
・頻出17個の気体の製法の反応式を全て書ける
・反応式の加熱の有無の見分け方
ではさっそくやっていきましょう!!
厳選17個!これさえ覚えればいい!
結論。頻出17個の気体の製法はこれです↓↓
①銅に希硝酸を加える⇒NO発生
3Cu + 8HNO₃ → 3Cu(NO₃)₂ + 4H₂O + 2NO
②銅に濃硝酸を加える⇒NO₂発生
Cu + 4HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O + 2NO₂
①、②はセットで覚えましょう。よく見ると反応式が似ています。濃硝酸なのか希硝酸なのかをよく見極めましょう。私はあきらめて、この順番に覚えました。
➂塩素酸カリウムを熱分解する(二酸化マンガンを触媒にする)⇒O₂発生
2KClO₃ → 2KCl + 3O₂
④過酸化水素の分解反応⇒O₂発生
2H₂O₂ → 2H₂O + O₂
➂、④は酸素O₂の製法です。ここもセットでどちらも書けるようにしましょう。
⑤二酸化マンガンに濃塩酸を加えて加熱する⇒Cl₂発生
MnO₂ + 4HCl → MnCl₂ + 2H₂O + Cl₂
➅高度さらし粉に塩酸を加える⇒Cl₂発生
Ca(ClO)₂・2H₂O + 4HCl → CaCl₂ + 4H₂O + 2Cl₂
⑦さらし粉に希塩酸を加える⇒Cl₂発生
CaCl(ClO)・H₂O + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O + Cl₂
⑤、➅、⑦は塩素Cl₂の製法です。塩酸の条件がそれぞれ違うことに注意しましょう。
⑧銅に熱濃硫酸を加える⇒SO₂発生
Cu + H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂
⑨硫黄を燃やす⇒SO₂発生
S + O₂ → SO₂
⑧、⑨は接触法で利用される二酸化硫黄SO₂の発生法です。接触法の記事はこちらから↓
接触法(硫黄、濃硫酸、酸化バナジウム)重要な性質を簡単に解説!!
⑩番以降は特にセットではありませんので、気合で覚えてください。
⑩硫化鉄に希塩酸を加える⇒H₂S発生
FeS + 2HCl → FeCl₂ + H₂S
⑪炭酸カルシウムに塩酸を加える⇒CO₂発生
CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂
⑫マグネシウムに塩酸を加える⇒H₂発生
Mg + 2HCl → MgCl₂ + H₂
⑬塩化アンモニウムに水酸化カルシウムを加えて加熱する⇒NH₃発生
2NH₄Cl + Ca(OH)₂ → CaCl₂ + 2H₂O + 2NH₃
⑭蛍石に濃硫酸を加えて加熱する⇒HF発生
CaF₂ + H₂SO₄ → CaSO₄ + 2HF
⑮塩化ナトリウムに硫酸(不揮発性)を加えて加熱する⇒HCl発生
NaCl + H₂SO₄ → NaHSO₄ + HCl
⑯ギ酸HCOOHに濃硫酸(脱水性)を加えて加熱する⇒CO発生
HCOOH → H₂O + CO
⑰酸素に紫外線をあてる⇒O₃発生
3O₂ → 2O₃
思ったよりも多かったですかね?逆にこの17個さえ完全に覚えてしまえば、無機化学分野の得点の土台ができると思えば、少ないと思えるはずです…(多分)。
残念ですが、1回で全てを覚えられる能力は私も含め、あなたにも備わっていません。毎日1回は必ずチェックして、反応式を書く練習しましょう。復習あるのみです。続いて加熱の有無について簡単に振れます。
加熱の有無の見分け方
まずは結論。加熱が必要な条件は以下の4つです↓
①固体どうしの反応には、加熱が必要
②熱濃硫酸との反応には、加熱が必要
➂脱水作用のあるもには加熱が必要
④加熱は丸底フラスコを用いる
上記の4つの性質を持っている反応式のほとんどが加熱を必要としています。言い換えると、この4つの条件にあてはまらないのものは加熱が必要ないということです。
以上の17個が、無機化学で超重要な気体の製法の反応式と加熱の有無となります。
誤りがあれば、コメント指摘していただけると幸いです。修正します。

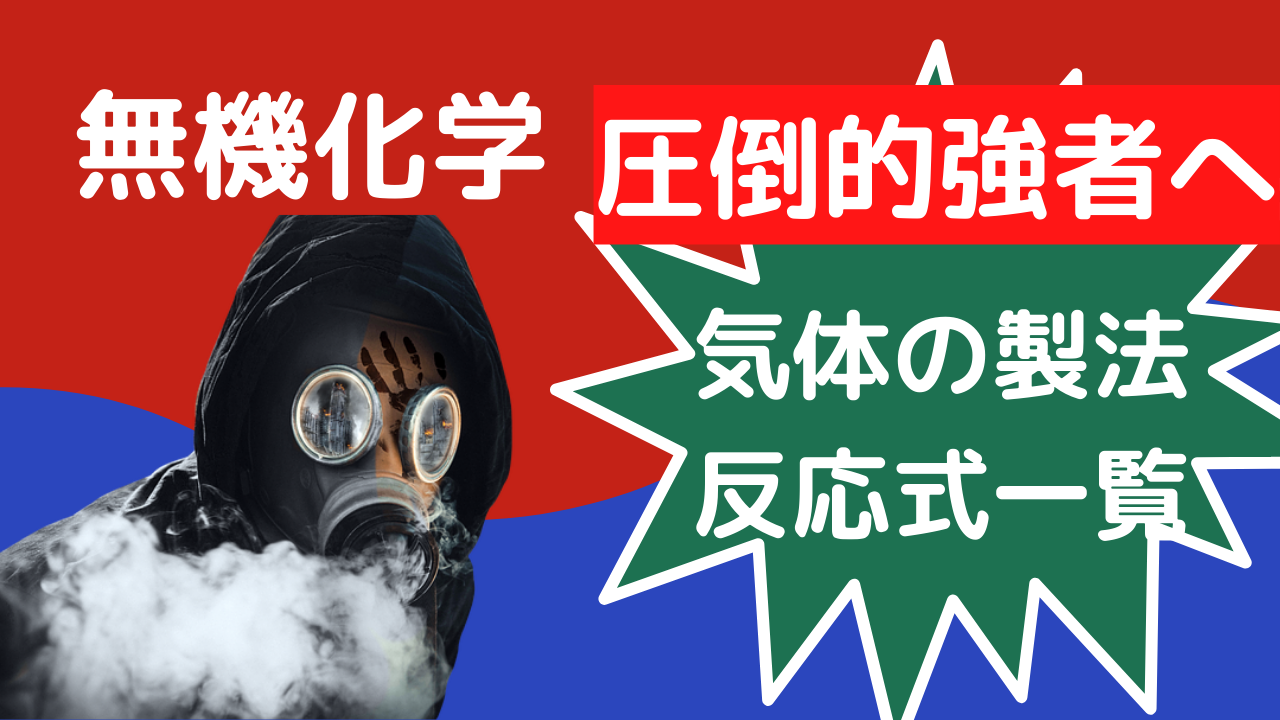

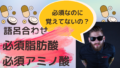
コメント